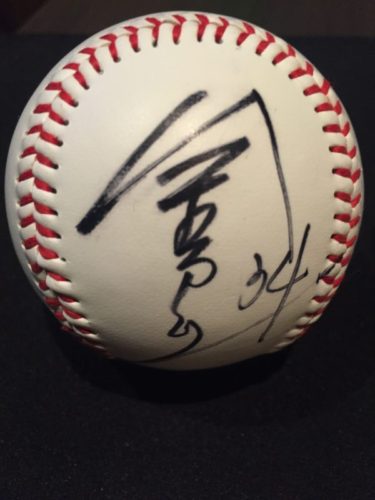*****
「自分はアーティストじゃない」と延藤さんは言う。
「仕事というのは現実のことで、それで食べられるかどうかが問題だ。現物を作っても売れなければ話にならない。商売にならなければ次が作れない。原型師、彩色師、いろんな作家に仕事をまわすこともできない」
アーティストじゃない。テーマや構図を考え、それぞれの原型師さんの特性を把握して 誰に発注するかを考える。原型師さんと相談しながら決めることもある。納期を定め、工程や品質を管理し、材料費、人件費、送料もろもろを計算し、すべてを統括する。
CCP制作のフィギュアがぎっしり並ぶ応接室で「どれがいちばんお気に入りですか?」とわたしは訊く。
延藤さんは答える。
「決められないですね。どれも甲乙つけがたい」
わたしは思う。
その言葉はこう言っている。
・・・自分の好みというのは意味がない。
売れなくては意味がない。売れなければ次のモノがつくれない。
延藤さんは考える。
「自分ではなく、客の見ている風景は何か」

******
客の頭の中にある風景は何か。
「ウルトラマンってね」と延藤さんは言う。
「印刷物の中のものをそのまま持ってきたのじゃ、ダメなんです。真っ黒けで汚いんですよ」
映像、写真集、いろんなものを見ながら、みんなの望んでいるウルトラマンをさぐる。
「何が欲しいのか、みんなの中に答えがある。いざ出されると、わーこれ欲しかったとなるけれど、イメージの中ではどうだかわからない」
「当時こうだったというものは、リアルじゃない。ホントのリアルを出しても客は買わない。正しい正しくないじゃない。カッコわるけりゃ買わないんだ」
客の声を聞きすぎると言われたこともある。客の要望に応えて何度も塗り直し、スタッフに負担をかけたこともある。こまやかなサービスと言えば言えるが、過度な無理は会社の体力を削ぎかねない。
だがそれもまた、客の内側の風景に近づこうとする模索のひとつだったかもしれない。

*******
何をつくるか考えるとき、延藤さんはパズルのピースをまずひとつ置いてみるのだという。まだ何もない盤面にやりたいピースをひとつ置く。それから他のピースを足してゆく。足りないピースは何だろう。原型師は、採算は、広告は。そもそもこれをやる意味は何だろう、と考える。
「置いてもどうしても図が埋まらないことがある。これでいいのか確信に変わらない。
このままゴールへ行けるのか、信念にならない」
確信、信念、という言葉を延藤さんは使う。
確かな保証がない中で、一回の失敗が命取りになりかねない道を歩いてきた。強い気持ちがなければ先へは進めなかった。
「売れるかどうかなんて、どの小売店に聞いても過去のデータでしか言わないんですよ。そこに責任をとれるのか、やってみなければわからない。これは実現でしか答えられない世界なんです」
結果を出すことでしか答えられない世界。
ここはいまだにリングなのだ。


そもそも小さな玩具メーカーのモノ作りは、さまざまな制約にさらされている。
まず当然ながら版権の制約。
たとえば延藤さんは仮面ライダーも好きだが、バンダイの絶対的な王国に踏み込むことはできない。人気のキャラを大手企業がタイアップでひき寄せるのとは訳が違う。
ウルトラマンも、最初は円谷から門前払いされた。版権がとれたのは全くの幸運だった。
キャラクターだけではない。
たとえば「可動」は売れる。正しい形より、売り上げだけなら、7ー3くらいの割合で、可動させたほうが売れると延藤さんは思う。だがその部分もまた大手に埋められて手を出せない。海洋堂もその壁に阻まれた。そこへの道は最初から封じられている。
延藤さんは、自分を奮い立たせるように言う。
「でも自分は無可動で感動した。
100年後、可動はどこまで残っているのか。
残っているのは無可動のほうじゃないか」
でももし可動が可能なら、と延藤さんはふと夢みるような口調になる。
「そのときは、自分の考えた関節、今までになかった関節を見てくれ、とかやっているだろう」

ソフトビニール人形は、まず原型から蝋型を成形し、メッキを施して金型をつくる。そこに塩化ビニールを入れて加熱し、固化させて取り出す。
比較的安価に或る程度の数を量産できるが、薄いものなどの成形は難しいとされる。そこは作り手の腕が如実にあらわれる。
人がいわゆるレトロな味わいのおもちゃを語る場合、ブリキなどの金物でなければ主にこのソフビ(塩化ビニル)素材を指している。どこか寸法がゆるんだ感じの、昭和な雰囲気をただよわせる懐かしいソフビ人形たち・ ・・。
だが天才原型師の出現が、この素材の可能性を一気に押し広げた。CCPがうしお氏を瞠目させる克明な写実でデビューしたのも、この素材でだった。
以後、CCPは、さまざまな素材を使いながら、基本的にソフトビニールを軸として、きわめて高度かつ繊細な作品を世に送り出してきた。
昨今3Dプリンタが開発され、撮った画像そのままの立体的な再現が可能になった。現時点でまだ課題は残すものの、既に実用化され、今後さらに進むと見られている。
コンピュータの力で画像を三次元に変換する、その克明な再現性は、圧倒的な写実を得意としてきた玩具メーカーへのまぎれもない脅威として控えている。
「写実でダメならデフォルメをやる」と延藤さんは言う。
「リアルなものへの感動や共感がダメになったとしても、いずれ時代はまた変わる。とにかく時代の空気を、客の頭の中を読むことだ」
そのための模索がずっと続いている。