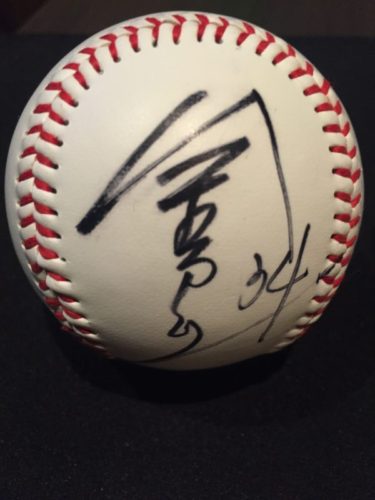CCPがこの7年間続けているプロジェクトに、CMCというシリーズがある。「CCP・マスキュラー・コレクション」の略で、「もし超人が実在したら?」というコンセプトのキン肉マンフィギュアシリーズだ。
「明日からゆでたまご先生と東南アジアにイベントに行くんですよ」
インタビュー当日、延藤さんはその準備にかかりきりのようだった。
現地でキン肉マンの作者を招いての格闘技のイベントがあり、そこにCCPも卓を出して商品を売るのだという。わたしはどうもえらく忙しい時に行ってしまったらしい。
平成29年、肉の年、「キン肉マン」関連イベントが活況をみせている。「ジャンププラス」では新しい連載もスタートした。この偉大な作品をめぐって、ひとびとは素敵な祝祭を楽しんでいる。
CCPのキン肉マン。


表情は漫画のキン肉マンそのもの、だが体は筋骨がりゅうりゅうと盛り上がり最高にリアルだ。
顔はキン肉マン。だが肉体は圧倒的なリアル。
でも「二次元を単に三次元に立体化したとき、これはキン肉マンじゃないといわれる可能性もある」と延藤さんは言う。
絵を単純に立体に置き換えるのではダメなのだという。
我ながらまったく素人じみているのだけれど、わたしは今までそんなふうにモノを見たことがなかった。平面のリアルと立体のリアルが違うという当たり前のことに、わたしはそのとき初めて気がついた。
確かに迫力ある絵には、現実とはミリ単位違う描き手固有の仕掛けが、細心かつ巧妙に仕組まれているはずだ。たとえば現実には見えないはずの死角の部分をちらりと描き込むとか、画力のある描き手なら、必ずカッコよく見せるための現実を超えた独自の工夫があるだろう。
しかもこれは格闘をえがいて人を魅了し続けてきた漫画なのだ。当然、特有の設定もある。
それを迫力ある立体として出現させるには、全く別の造形の論理、全く別の仕掛けがどうしても必要なはずだった。
そうか、とド素人のわたしはそこで初めて思い至る。
ウルトラマンやスペクトルマンには特撮としての映像がある。でもマンガなどの二次元表現をフィギュアにするのは、ぜんぜん別の作業なのか。

***********
もうひとつ、漫画「キン肉マン」をフィギュア化することについて、延藤さんは言った。
「キン肉マンは何十年も続いている。その中で、ぼくらが今の絵を単純に三次元に置き換えるだけでは評価されない。あえて昔の絵を今の筋肉で立体化してみたりする、そのギャップがウケるんです」
二次元を単に三次元にするのでないというあの言葉は、二重の意味をもっていた。
先に言った、絵の仕掛けを立体の論理へ変えること。
加えて、時間を隔てたものを組み合わせ、現実にはあり得ない味わいを提供する。ただの変換でなく、さらに記憶を上回る新しさを。
その味を理解し賞翫する人たちがCCPの常連客なのだ、とわたしは遅まきながら気がついて衝撃を受けた。
延藤さんの言う「客の頭の中を読む」とは、この洗練の中で戦うことだったのか。



************
先にも書いたとおり、「CMC」は「もし超人が実在したら?」というコンセプトで作られる、CCPのキン肉マンシリーズである。
体型や体脂肪率なども計算する。得意技によって筋肉の付き方も考える。
そもそも現実にはあり得ないモノをあり得させる試み・・・異様さの顕現と、その肉体的かつ精神的な掘り下げという意味において、画期的な挑戦が続いている。
思うのだが、「実在させようとする」とはなんと恐ろしいことか。
それは常軌を逸しており、深くて、輝いている。
「実在」への深い執念、おもちゃの魔力の根源は、たぶんそういう所にあるのだろう。
そして洗練。
キン肉マンの世界である格闘技、とりわけプロレスというセンシティブなジャンルは、 現場の興奮と同時に、それとはまったく異なる熱をひそませている。
「文脈」を味わう情熱だ。
さまざまな技や名勝負を記憶し、俯瞰し、解釈し、文脈を組み合わせ、差異や約束事を面白がること。それは、その分野とそれを見る人々の成熟・洗練なしには成立しないが、わたしたちは今まさにおもちゃにおいても、そういう目をもつ人たちの時代に生きている。

キン肉マンの作者・ゆでたまごの嶋田隆司氏は、2010年刊『マンガ脳の鍛えかた』(集英社)で次のように語っている。
「できそうでできない技を作るのは、たぶんゆでたまごだけのテクニックだと思います。僕の原作の段階では絶対に理論上は普通の人間にはできないっていうような技でも、中井君(キン肉マン作画担当・中井義則氏)が「絵のうそ」で描いてしまう、という…」
「昔からの技と今の技、両方描くことができるのが、すごくおもしろいんです。キン肉スグルと万太郎みたいに違う世代が戦う時は、あえてキン肉マンにはオーソドックスな昔のプロレスをやらせて、万太郎たちにはタックルや格闘技みたいな総合格闘技のスタイルをやらせたりして。プロレスラーのアントニオ猪木と総合格闘家のヒョードルを戦わせるようなことがマンガの中でできるわけです(笑)。そのギャップを、物語としておもしろく使う」
現実にはありえないようなわざを絵のウソで見せる。昔のわざと組み合わせて時間的なギャップを演出する。
「キン肉マン」作者の数年前の発言が、延藤さんの言葉と不思議に響きあう。
マンガ表現の成熟とおもちゃ表現の成熟がまじりあって、CMCに現れているように思われる。

**************
インタビューのあと、応接室に並ぶ作品を写真に撮らせてもらった。シャッターを切りながら、棚にぎっしり並ぶモノたちの存在の強さに押された。
ワンダーフェスティバルがスタートして30年近くが経つ。ガレージキットの世界に光を当てたこの巨大なイベントが日本の文化にもたらした影響はあまりにも大きい。かつて、企業に作られたプラモデルやガンプラは既に高い水準で人々を魅了していたが、フィギュアを、個人の繊細かつ高次な感覚という底知れぬ領域にしんじつ踏み込むことを可能にさせたのは、このワンダーフェスティバルだった。
おもちゃは、原型師という天才たちを先導に、レトロな実体験の世界から身を引き剥がし、存在のリアルと洗練への道を急速に駆け上がってきた。
懐かしさという概念は、もはやレトロやファンタジーだけのものではない。それは、実体を備えるはずのなかった子供時代の夢想が目を疑う圧倒的なリアルで出現する、その総毛立つような感覚のことではないか。
CCPの格闘と挑戦は、子供じみているといわれた夢想が日本のカルチャーの最前線となってきた歴史の記録だが、その道を延藤さんは造型師や客たちとともに一歩一歩進んできたのだった。
客たちは文脈を見、同時に、その文脈を超えた何ものかの出現を見る。それはそのジャンルとキャラクターへの深い理解に支えられており、3Dプリンタの抜き型的な表現では及びもつかないものだろう。




***************
結局のところ、モノをつくるとは仕事をつくることで、仕事をつくることがモノをつくることだった。それはすなわち、未来に向けて前のめりで新しい価値は何かと問い続けることだった。
延藤さんは言う。
「最初にキン肉マンをつくったとき、そんなモノ売れないという声もあった。売れてもせいぜい300個くらいじゃないかと言われたんです。でもそれを押し切って出して1000売れた。あそこで負けていたら1000はなかった」
何に負けるのか。否定する人に負けるのか。
いや、おそらくは、自分の中の不安、これで良いのかためらいひるむ心と戦っている。
版権は常にきびしく、写実はダメになるかもしれない。
可動は大手に封じられている。
それでも生き残る道はある。
勝機は必ず潜んでいる。
次の価値は時代の空気の中、人々のまだ見ぬ頭の中に在る。そのイメージに目を凝らし、現実の世界に引きずり出す。
あの日、ワンダーフェスティバルで、おもちゃが大人の世界の中央に立っていた。
そのとき、子供時代から続く古いおもちゃ観が破れ、魂が震えた。
まるでその存在が天から落ちてきたように。
あの日から延藤さんにとっておもちゃとは、世界を塗り変える新しい価値のことだった。
おもちゃを仕事にして生きてゆく。
諦めない。
このリングに立ち続けるため、倒されても前へ向かってゆく。
< 2017年9月 >