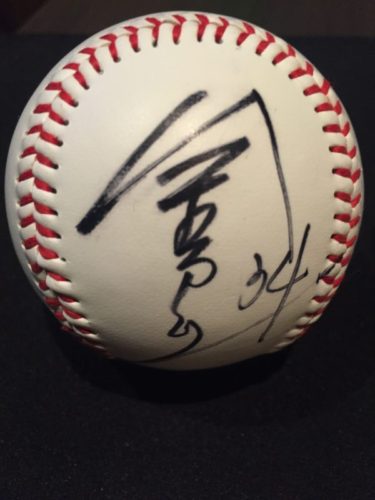延藤直紀(CCP代表)
1968年北海道生まれ。幼少よりヒーローに親しみ憧れ、航空自衛官(レスキュー隊員)として活躍ののち、1990年キックボクサーに転身。翌年「全日本キックボクシング連盟新人賞」受賞、最終的に全日本2位・世界3位まで進むが故障により引退。
2000年に(株)CSSキャラクター事業部としてフィギュア製作を開始、 2001年独立しCCP(キャラクター・コンテンツ・プロダクション)を設立(翌年法人化)。気合いでおもちゃを創り続ける最強社長である。

(2017年9月)
http://www.ccp.jp/replica/index.html
blog.livedoor.jp/ccp
CCPがウルトラマンパワードを発売した。エクスプラス/少年リックはパワードのリアルマスターコレクションを再版した。バンダイのアルティメットルミナスプレミアムは、ウルトラマン弐で青目のウルトラマンジードプリミティブを発売した。
さまざまな時代にさまざまなウルトラマンがいて、多くの作り手をさまざまにインスパイアし続けてきた。
どの品を買うか(もちろん全部買う人もいる)は、その人の好みとしか言いようがない。それぞれの経験が、好きな質感、形状、世界観を決めている。
だが、自分が否定していたはずのモノでさえ、当の造型を目にした瞬間、心を鷲掴みされてしまうことがある。
それまでぜんぜん意識もしてなかったけれど、自分は本当はずっとこういうモノを見たかったのかもしれない。そんな、本人すらうろたえるような事態が突然天から落ちてくる。
造型の恐ろしい魔力はそういうものだ。
それは時に不意打ちのごとく人々を襲い、人は圧倒的な存在を前にしてただ賛美せずにいられなくなる。
さてここにひとつの小さな玩具メーカーがある。
スタートして20年足らず。まだ老舗というほどではないが、さまざまなソフビを発売して一部に熱狂的なファンを生んできた。社長は異色の格闘家あがり。激しいしのぎ合いの続くおもちゃ業界で、みんなの心をつかむモノは何かを日々考えている。
どんなモノをつくれば皆は喜ぶのか。
どんな風景を創造すれば皆は震えるのか。
まるでその風景が天から落ちてきたように。

**
CCPが最初に作ったのはスペクトルマンのフィギュアだった。
「スペクトルマン」は1971年1月から翌年3月まで放映されたピープロダクション制作の特撮ヒーロードラマである。宇宙からの侵略者ゴリの送り込む怪獣とスペクトルマンが闘うストーリーで、当初のタイトルは「宇宙猿人ゴリ」。
作品づくりにあたっては、或るマニアが当時の雑誌を大量に提供し、別のマニアが何時間もかけてグラビアをカラーコピーした。さまざまな資料をもとに構図が決まり、当代一流の原型師が腕をふるって最初の作品ができあがった。
ピープロの代表であり、スペクトルマン原作者でもあるうしおそうじ氏は、完成した作品の写真を見て「こんな写真は撮ったことがない」と言ったという。
CCPが制作したフィギュアの写真を、うしお氏は当時の本物の写真だと思った。
CCPは、そのおそるべき克明な写実性でデビューした。
力量は最初から際立っていた。
戦うスペクトルマン 『冒険王』1971年夏休み増刊号
***
延藤さんはもともと航空自衛官だった。そのあとキックボクサーに転身し、プロとして 国内2位・世界3位のところまで行った。
だが故障から引退することになり、今後の身の振り方を決めるにあたって、さてどうしようか、格闘技の経験を生かしてジムでもやろうかとぼんやり考えていた。90年代末のことだった。
そんなとき延藤さんは、ワンダーフェスティバルに行った。ワンフェスは年2回ひらかれる巨大な造型の祭典で、当時は東京国際展示場でやっていた。ちょうどディーラーとして卓を出している知り合いもいた。
延藤さんはそこで、或るフィギュアに目を奪われた。

****
延藤さんはひとつのフィギュアに目を奪われた。
それは或る天才原型師の制作したソフビ人形「帰ってきたウルトラマン」だった。
もともとおもちゃが好きだった。子供時代からウルトラマンや仮面ライダー、ジャンボマシンダーなどのおもちゃにかこまれて育ち、東京に出たらその熱が再発して、おもちゃは身近なものだった。
だがそのフィギュアを見たときの衝撃は大きかった。
延藤さんは言う。
「自分はずっと、おもちゃは子供のモノだと思っていた。それまでおもちゃが好きだと言うと、子供だといってバカにされるのが普通だった。でもそこに在ったのは、完全に大人の世界だった」
当時、村上隆が、等身大フィギュア等をさかんにワンフェスに出品し出していた頃だ。
おもちゃや造型の概念そのものが大きく胎動していた熱い時代だった。
その場所に、世界観を塗り変える圧倒的なウルトラマンが存在した。
これをやろう、と延藤さんは思った。
大人としてこの世界で食ってゆく。
自分自身でこれを発信する側にまわる、それは趣味や憧れの次元でなく、今後の身の振り方として浮かんできたのだった。