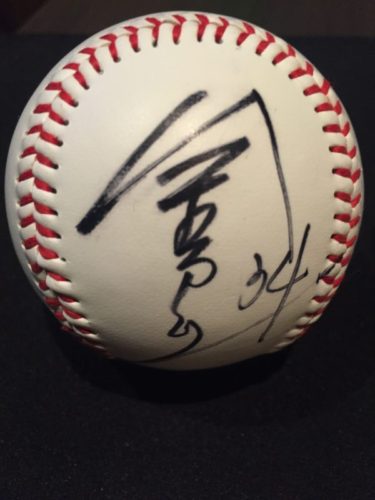Mr.AE/おもちゃプレイヤー
196X年生まれ。幼少期、ミニカーとの運命的な出会いによっておもちゃに目覚め、青少年期、タカラのSF玩具でおもちゃコレクターとして開花。以後、自らのおもちゃ道を邁進する。一時はフィギュア暗黒面に染まるも、ドール愛の理力の導きによって、再びおもちゃの真髄に立ち戻り、現在は博物館展示用アイテムの蒐集に奔走する日々を送る。
今回のアイテムはミニカーHotWheels
(現在、日本ではホットウィールと呼ばれていますが、ここではAE氏がハマった時期を尊重し、当時一般的だったホットホイールという呼び方で統一します)
Contents
HotWheels ホットホイール(米・マテル)

(2017年5月)
トランプ大統領が誕生し、日米自動車論議がかまびすしい。
日本がアメリカに車を売りつけるばかりで買わない、それは不公平ではないか、という件だ。
もちろん日本人としては異論がある。だがそれが、アメリカのごく一般の人たちの間でずっと醸成されてきた長い憤懣だという、その当たり前の深さにひるむ思いがする。
ハリー・ベントリー・ブラッドリーは、1960年代半ばを振り返り、次のように言っている。
「デトロイトの一部のカーデザイナーは、カリフォルニア行きを熱心に考えていた。日本人がグロテスクな小さい車でアメリカに入り込んできていたからだ。クオリティは高く燃費は優秀、でもすごく変なルッキング。日本人が本社を置いたカリフォルニアに行けば、やつらにデザインのコンサルティングをして良いビジネスができる」(Randy Leffingwell「HotWheels 35 years of speed,power,performance and attitude」)
さて、今回の語り手AEさんは、わたしの知る限り、現代日本の最も深遠なオモチャマニアの一人である。
その一流の審美眼と直感によって集められた膨大なコレクションは、特定ジャンルにとどまらないドールやソフビ、ロボットなどまさに「おもちゃ」の集合体だが、その氷山の一角にミニカーがある。ミニカーはAEさんにとっておもちゃ体験の原点であり、今も氷山を産み出し続ける氷河でもある。
ミニカー。それも特にアメリカ・マテル社のホットホイールだ。
正確には1968年の発売からほぼ十年間続いたレッドラインというタイヤのシリーズに執着している。
より厳密にいえば、68年から73年、エリオット・ハンドラー社長のヴィジョンのもと、あのハリー・ベントリー・ブラッドリーがデザインを立ち上げた、甘美な出発から数年間のホットホイール。

1 3歳のAEさん、ミニカーに狂喜する・・・おもちゃ体験の原点
AEさんが初めて出会ったミニカー、それはマテルでなくマッチボックスのダッジチャージャーだった。
1970年頃のことだ。
AEさんが3歳のクリスマスの朝だった。
目を覚ますと、枕元に箱が置いてあった。
てのひらサイズの箱の表面には、未知の言語がビッシリ書かれていた。
透明な窓から覗くと、中には青い小さな車が停まっている。
車とは道路を走る乗り物だ。
それはすでに子供のAEさんも知っていた。
だがそれがなぜ今、こんなふうに手のひらの上におさまっているのか。
こんなんじゃ人は乗れないじゃないか。
それは、そののち長いおもちゃ人生を送ることになるAEさんが、生まれて初めておもちゃという概念に触れた瞬間だった。
現実に存在する大きなモノが、小さくなって自分の手のひらに乗っている。
そうしてさわれる、いじれる、遊んだりできる。
そうか、こうやってモノを小さくしていじるって楽しみ方があるんだな。
AEさんは子供心にそのとき気が付いた。
それは漠とした、途方もない広がりの予感だったかもしれない。
何かを小さく凝縮して思い通りにする、世界中のモノを手元にもってくる、そういう手段が存在する。
それがこれだ。おもちゃだ。
3歳のAEさんは狂喜した。

マッチボックス ダッジチャージャー
当然の流れと言うべきだろう。3歳にしておもちゃの洗礼を受けたAEさんは、ミニカーに狂った。
明けても暮れてもミニカー、ミニカー。
あの子の家に行くにはミニカーを持って行かないと怒られる、親戚たちはそう言うようになった。
スポンジが水を吸うように、子供のAEさんはミニカーの名前をどんどん記憶した。外に出たとき、あれはダットサンのセダンだ、とかすぐ車種を言って、すげえ子供だと驚かれた。
2 ホットホイールとの出会い・・・車って走るんだ
そんな或る日のことだ。AEさんはおじいちゃんの家に行き、近くのスーパーの片隅で風変わりなミニカーを見つけた。
1970年頃、普通のミニカーは箱に入れて売られていた。だがそのミニカーは、紙にプラスチックの覆いをかけて、柱にぶら下げられていた。正確には画鋲で張り付けにされていた。箱以外の包装は初めてで、AEさんはまずびっくりした。あとで知ったがそれはブリスターパックという手法だった。
その車の奇抜な色にも驚いた。
塗膜が透き通って、金属の地金が輝いて見える。
メッキという存在は知っていたが、表面が光るメッキとは異なり、透けた紫色の向こう側にあるボディが輝いていた。
デザインも妙だった。屋根は透明なドーム状で、コクピットは丸見えだ。こんな車は見たことがなかった。
大判の台紙には巨大な流れる炎のような文字で〈ホットホイ~ル〉とある。そのそばに不思議な言葉が書いてあった。
「世界一はやいミニカー」

「世界一はやいミニカー」
速いって何だろう?
AEさんはそう思い、「あ、車って走るよなぁ」と不意に気がついた。
その頃普通にお店で買えるミニカーはトミカだった。
国産メーカーのトミカは、実車の再現性に長じ、さまざまな車種を発売していたが、特に走らせて遊ぶという感じではなかった。ガレージにしまうなど静的な遊びが主だった。
・・・これは自分の知ってるミニカーとは違っている・・・
恐る恐る手にとってみると、トミカよりやたらに重い。
バックの中でミニカーがガタゴトしないよう、丁寧に紙製のおさえが仕掛けてある。
AEさんはパッケージの裏を見た。ものすごいことが書いてあった。
「ホイールがしっかりしている」
「独特のサスペンション」
「まさつの少ないホイールベアリング」
「オイルはぜんぜん必要なし」

何なんだ、これは?
子供心にAEさんはびびった。
「まさつ」って何だ、オイルって何のことだ。そもそも「走る」って、どうやって走らせるんだろう。
パッケージには「ホットホイールのセットで遊べば、より速くより遠くつっぱしります」ともあった。
セット?
そこで目を上げると、子供の手が届かないような高い場所に「ホットホイールレーシングなんとかセット」という巨大な箱が置いてある。
セットという言葉も初めてだった。
…これは単体のミニカーじゃない。ミニカーに何か付いてるのか。
オレンジ色の狭い道路をミニカーが突っ走っているイラストに、AEさんははっとした。
…そうか、道路が付いている!そこでミニカーを「走らせる」のだ。
( 知ってるか?車は走らせてなんぼだぜ、坊主 )
それがAEさんと、アメリカ・マテル社「ホットホイール」との、最初の出会いだった。

3 ホットホイールの魅力をこまかく語る
アメリカ・マテル社は、バービー人形で既に有名なおもちゃ会社だったが、1968年ミニカー業界に疾風のごとく参入し、後にsweet sixteenと呼ばれる16車種を発売して驚異的な成功をおさめた。
いや、単に16車種ではない。形は16種、そのそれぞれに数種類の塗装色を設け、子供たちは店先で「好きな車」を「好きな色」で選んで買えるのだ。まるで大人が実車をディーラーから購入するように。
色合いも、実車とは全く異なる「ダイキャスト素地にクリアーカラーを吹き付ける」手法を導入、ホットホイールは、キャンディペイントとかスペクトラフレームと呼ばれる宝石のような塗膜を纏うことになった。
デザインがまた圧巻だった。アメリカ特有のカスタム車文化「ホットロッド」の息吹を受け、実車とはどこか違うという、間違い探しを楽しむような味があった。実車を元にはしていても「実車名の頭にcustomを呈する」というネーミングもホットだった。とにかく熱いのだ。
恐るべき開発陣営は、さらにホットホイールに世界初の魅力を与える。・・・・走行性。
< 車は走らせてなんぼだぜ >
摩擦軽減用ポリキャップの周りを滑るように廻るタイヤ。ピアノ線を使った四輪独立懸架サスペンションを仕込む車種まで存在し、ビスケットの欠片が散乱するテーブル上を、四輪全てが接地して安定的に走れるというすごさ。
「傾いたテーブルなんかに置くと、スーッと走ってしまって、どこまでも走り続けるんですよ」
取材現場となったカラオケボックスのテーブルの上、そこを走るパイソンというレッドラインを見つめながら、AEさんは嬉しそうに言った。
当時日本にも輸入された「セット」だと、ミニカーもコースも全部ついていて、そこですぐに走らせることができた。
もちろんセットを買うお金がない人もいる。セットに付いてきた車が好みのものでない場合もある。当時500円かそこら出すと、レールだけ15メートル分くらい入っているセットを買うことができた。AEさんはそれを買い、まずは手持ちのトミカを走らせてみた。だが何かうまくいかない。そこで新しく買ったホットホイールを試してみると、これが面白いようにスーッと走る。根本的に設計が違うのだ。
3歳から5歳頃のAEさんは、そのコースで一日中ホットホイールを走らせた。この車が走ること走ること。楽しくてしょうがない。Aさんはいつまでもいつまでもそれを眺めていた。



取材の日、AEさんは、持ってきたホットホイールを裏返して見せてくれた。
「この車種は結構初期のものなんですが、ここ、見えますかね。タイヤのところにピアノ線が入っているでしょう。これ最高の解像度で撮ってください。四角い穴の中のピアノ線が写ると嬉しいな」
裏返した車のシャーシに空いた穴の向こう側、白い腱のようなピアノ線が覗いている。


「1軸に1個のタイヤが付いて、四輪それぞれサスペンション機能が働く、これホントの車と同じ。あとこわくて分解したことがないけど、これ、ホイール部分が軸から外せるんですよ」
・・・なるほど、分解改造できるんですか。
「そしてこれが一番強調したいところなんですが・・・」
AEさんはホットホイールをテーブルに降ろして、ルーフに人差し指を当ててからそうっと押し下げた。
「沈むでしょう、ほら。」
AEさんが押すと、その車がゆっくりと沈んでまた戻るのが、傍目にもあきらかに見えた。
「さらに一輪一輪を押しても、それぞれがバラバラに沈むのです」
・・・おお、これが先程の四輪独立なんとかなんですね。
「ただしこの後少ししてから発売される車種では、この機構は割愛されてしまう。同じレッドラインタイヤでも、トミカみたいに1軸に2つのタイヤが繋がって、ポリ製の板でサスペンション機能を設ける形になる。さらに後になると、サスペンション機能がオミットされちゃう。コスト削減とは言え、これはちょっと哀しいですね」
AEさんはホントに哀しそうな表情になった。
4 ホットホイールとの再会・・・自分が知っていたあれはどこへ行ってしまったのだろう?
さて、AEさんの興味は、少年期になるとミニカーから他のおもちゃの蒐集に移行した。この話はいつかまた詳しくすることになるだろう。
ただともかくも、このちびっこは、絶えずおもちゃと共に在り、おもちゃを通して社会の仕組みを学習した。いい子にしてなければお小遣いがもらえない。お手伝いをすればお小遣いがもらえる。おもちゃが欲しいからいい子でいる。
まったく良い教育だったものだ。
おもちゃを買うために生きていた。
そして1980年代、すっかりミニカーのことを忘れていたAEさんは、おもちゃ屋でホットホイールに再会した。ツインミルという特徴的なデザインは、間違いなくホットホイールの一車種だった。

そういえばホットホイールってあったよなあ。・・・あれ、でも箱に入ってたっけ?
なんだか変だった。
その頃店頭に並ぶホットホイールは、ミニカというブランド名の刻まれた赤い紙箱に入るようになっていた。
試しに買ってみるとタイヤも固く、弾まなくなっていた。音も違う。
気がついて周囲を見渡すと、昔のままのホットホイールはどこにも見つからなかった。
それでは自分が知っていたあれは、一体どこへ行ってしまったのだろうか?

マテル赤箱
********
さらに時は経つ。
AEさんはいっぱしのおもちゃコレクターとして成長し、社会人となった。
かれの知っていたホットホイールは完全にどこからも無くなっていた。
ある日、なんとなく虚しさをを感じたAEさんは、家の押入をごそごそやって、当時いちばん遊んでいたホットホイールを発掘した。
紫のスペクトラフレームのシルエットという車種。一番初めに買ったブリスターパックのやつで、度重なるコース走行に塗膜は剥がれ、ホイールのメッキは擦れて無くなっている。だがテーブルに降ろした時のカチャッという接地音、サスペンションのグッという沈み込みは健在だった。
・・・そうだ、これだこれだ。
懐かしい感触がAEさんの内部に火をつけた。
俺は、自分にとっての真の「ホットホイール」をもう一度集め直したい。
いや、集めるのだ。当時なかった財力がいまの俺にはある。「みずから自由にできる力」があるんだ。かつては買えなかった車まで、思いのままに買ってやるぜ。
それは多くのコレクターを突き動かす原動力ともいえる感情だった。
いつのまにか周囲の世界から消えていた<ホットホイール>を、俺はこの手で取り戻してやる。
AEさんは国際的なネットオークションのebayに登録し、かつてのホットホイールを猛然と探し始めた。
5 消えたホットホイールを求めて・・・直面した問題
AEさんは、かつてのホットホイールを猛然と探し始めた。
その頃を振り返ってAEさんは言う
見つけたモノは当時それほど高くはなかった。
ただし、取引することができさえすれば、と。
買い始めてすぐわかったのは「not sell internationally」があまりにも多いということだった。
ホットホイールは基本的にアメリカ以外に売らない。
ほとんどは外国との取引が面倒という理由だが、それ以外にこれがあった。
「アジアには売らない。日本人には売りたくない」
(お前らホットホイールをわかってない。
どうせ転売するんだろう? )
またそういうディーラーに限って、極上のホットホイールを持っているのだ。
AEさんは早くも日米自動車交渉の山に乗り上げた。

AEさんがebayで最初に学んだことは、ホットホイールをアジアに売らないという人の多さだった。
< お前らにホットホイールはわからない。
どうせ転売するんだろ?>
とある個人的な販売サイトに、AEさんがどうしても欲しい車種を見つけたときのことだ。
交渉で食い下がるAEさんに相手は言った。
そんなに言うなら根性を見せろ。おまえが本当にホットホイールが好きだということを証明してみせろ。
たまたまAEさんは上司から海外駐在を薦められていた。これはまさにチャンス!
業務内容や滞在場所をなんとかやりくりしたAEさんは、生まれて初めて海外へ飛んだ。初海外で苦戦しながらも、宅配便のやりとりが可能なモーテルを仕事現場の近くに見つけて転居、満を持して例の販売サイトのコレクターに連絡した。
「俺はいまアメリカに来た。アメリカに居るぞ。どうだ、これで国内取引だ」
「いま希望する車種をカートに入れた。さあ、振込口座を教えてくれ。俺にホットホイールを売ってくれ」
お前の勝ちだ、と相手は言った。
お前を信用しよう。お前はほかのアジア人とは違うようだ。カートを見てもそれがわかるよ。
リストの中のもっと価値のある実車モノには目もくれず、自分の好きなモノを入れている。
わかったよ、お前は自分が欲しいモノを買いたいだけなんだな。
そう、AEさんの好むものは、一般的に価値を認められている「実車ベース」のホットホイールではなかった。
当時あまり人気の無かった「架空モノ(ドリームカー)」を、AEさんはひたすらカートに詰め込んでいたのだった。



アメリカ特有のカスタム車文化ホットロッドは、主に1930年代のフォードなどクラシックカーを基体としてそれをアレンジする。車体を低く、派手なペインティングを。
ホットホイールの初期デザインを牽引したハリー・ブラッドリーは、こうした輝かしいカスタムカーの歴史に名を刻む人物だ。
かれがマテルに加わって、手探りでミニカーのデザインを始めたとき、「ブラッドリーは、それが(マテルの)かれらが求めているものであることを望みながら、未来の車の図面を描くのをスタートした」という。
「1984年の車が1966年にバックして来たみたいだと自分が思うようなものを」とブラッドリーは語る。
「(社長の)エリオットはいつも立ち寄って、ぼくの描く技術にすっかり惹かれているようだった・・・」(Randy Leffingwell『HotWheels 35 years of speed,power、performance and attitude』)
あとに続く綺羅星のようなデザイナー陣も負けてはいない。
実際の車をそのまま再現したものでない、未来的なデザイン、いじりまくった、風変わりで目を驚かすようなミニカー、そういうものはホットホイールの大きな魅力となった。
AEさんは知らず知らずの内、ホットホイールの中でもとりわけ現実にはありえないような、仮想的なタイプを夢中になって集めていた。
当時日本の小売店では入荷しなかった、カタログの中でしか見られなかったドリームカーを。

5 マテルの実車は一見普通に見えるけれど、どこかが、何かが、変なんだ・・・本物のリアルに目覚める
結局AEさんは、そのアメリカ滞在で8万円分くらい買った。
帰国後もその相手は、手元にあるダブりの品などをみんな売ってくれた。だいたいその1年で50万円くらいかけて、好みのホットホイールを揃えてしまった。
相手はまた、それまでドリームカーを闇雲に買うだけだったAEさんに、一般的な価値も勉強したほうがいいと勧めてくれた。
マテルの実車は一見普通に見えるけど、どこかが、何かが、変なんだ。
新しい素敵な概念を知ったAEさんは少しずつ勉強し、マテルは実車の名がつくタイプも必ず手を加えて彼らなりのモデルにしているのを知った。
それで徐々に実車タイプも集めるようになった。
「必ずどこかいじってる、それがホットホイールの魂なんですかね」とAさんは言う。
そういうのにびりびりしびれるのだ。
リアルとは、単に現実に即しているということではない。
ただの再現性とは全く別の次元で、本物の魂を感じさせるかどうか。
人が自分の空想をどこまで本気で実体化し、おのれの手中に持ってこようとしているか。
いかれた空想と、サスペンション。
ホットホイールはAEさんを、自分にとっての本物のリアルに目覚めさせた。



- 1
- 2